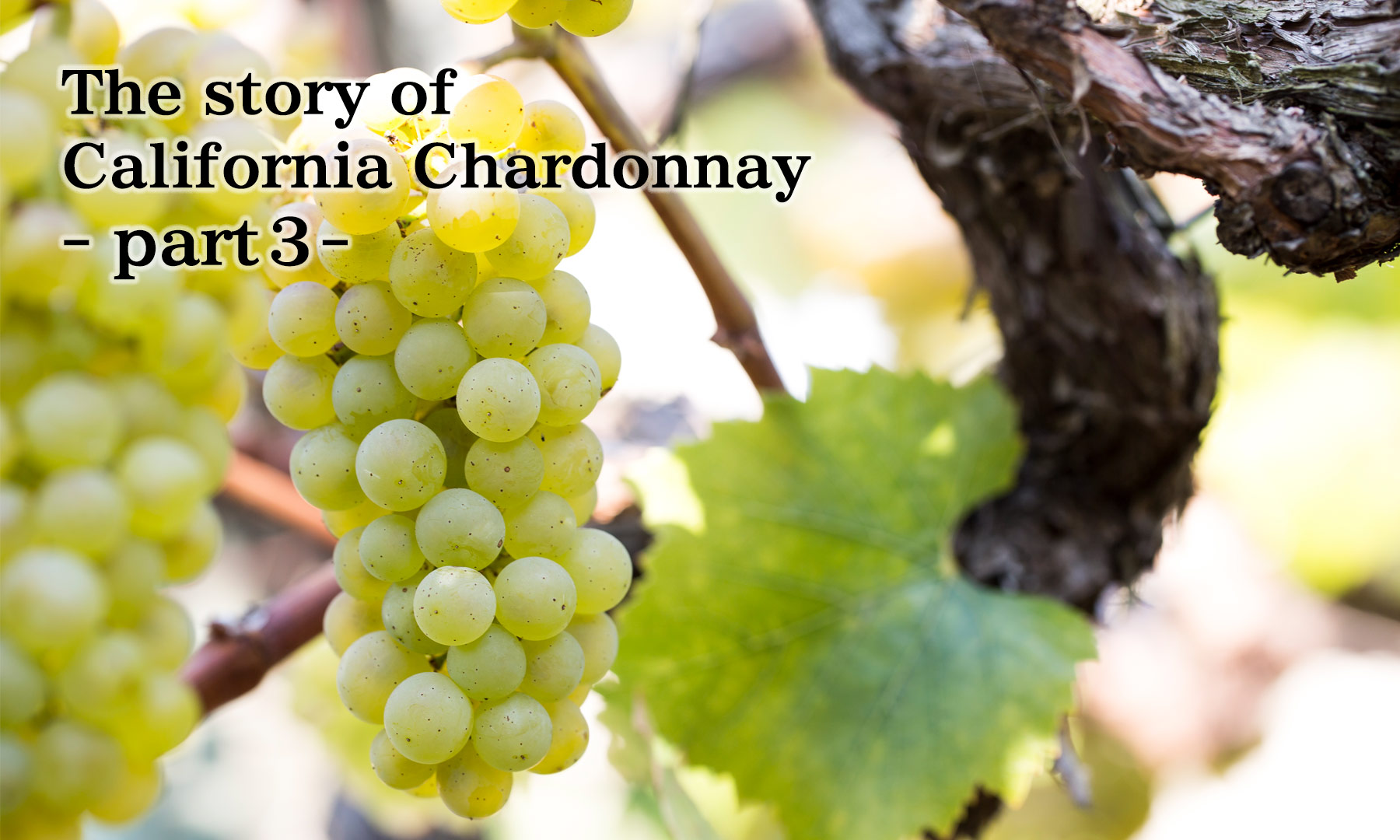カリフォルニアワイン協会日本事務所では、ワインライターであり教育者でもあるイレイン・チューカン・ブラウン(IWSC インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティションによる2020年「年間最優秀ワイン・コミュニケーター」受賞者)が、「JancisRobinson.com」のために執筆した「カリフォルニア、シャルドネの物語」(全4部、原文は2018年12月に発表)の日本語版(ヴィニクエスト代表小原陽子氏による翻訳)を作成いたしました。
※日本語版eBook(パート1〜4統合版)は、こちらからダウンロードできます。
※JancisRobinson.com掲載の原文(パート3)はこちらから。
************************************************
カリフォルニアのシャルドネのグローバル化:1980年代から2000年代
1970年代が終わるころまで、数少ない例外を除きカリフォルニアのシャルドネのほとんどは破砕後に一定期間のスキン・コンタクトを行い、温度コントロールされたタンクを用いた培養酵母による低温発酵を経て、MLFを行わず新樽で熟成させて作られていた。その結果、リリース時点でフレーバーにあふれた、インパクトの強いワインが大量に作られることとなった。ただ興味深いことに、当時のワインのアルコール度数は後のカリフォルニアのシャルドネほど高くなく、多くが13%あるいはそれを下回っていた。最も高いものですら13.5%を超えてはいなかったのである。
1981年にフランク・プリアル(Frank Prial)が書いたニューヨークタイムズの記事が、こうして確立されたカリフォルニアのシャルドネのスタイルに次なる大改革をもたらすきっかけとなった。プリアルは特定のワイナリーの名前は出さず、ただ「有名なノース・コーストのワイナリー」とだけ記したが、この地域のシャルドネについて大まかに解説したのち、彼がそのワインに感じた問題点を指摘したのである。彼の批判は当時流行を生み出した生産者たちの多くが目指していた「すぐに楽しめる味わい」に真っ向から異を唱えるものだった。彼は2本のワインをディナーに持参し、うち1本はカリフォルニアのシャルドネ、1本は白のブルゴーニュだったとしている。「どちらもシャルドネかつ最良のヴィンテージのもので、価格帯も同程度のものでした。最初はカリフォルニアのシャルドネのほうが印象的で、フランスのワインは弱く味気なく感じました。ところが食事が始まって20分も経つと、アメリカのワインは無粋な力で圧倒し始め、フランスのワインは対照的にその魅力と繊細さを少しずつ垣間見せ始めたのです」。
デイヴィッド・レイミー(David Ramey)は、プリアルの記事がカリフォルニアワインに重大な影響を与え、それによって生産者たちが自分たちのワイン造りを再考し始めるようになったと指摘した。記事が発表されたタイミングもまた決定的だった。カリフォルニアのノース・コーストでは近年の歴史上初めてワイン造りに関わる仕事があふれ、経営者たちが品質と名声のために投資を惜しまない時代となっていたからだ。 パリスの審判が大きな原動力となり、UCデイヴィスで栽培と醸造を修めた若者が続々と輩出され、教育を受けたワインメーカーを求める空前絶後の需要と重なったことも幸いした。その頃にはアメリカとヨーロッパの間を行き来することははるかに容易になり、好調な経済は十分にそれを実現可能とした。これらの要素が相まって、カリフォルニアワインは完全に新たなる方向へ進み始めたのである。1970年代終盤から1980年代にかけ、当時駆け出しだったワインメーカーたちが現在「カリフォルニアの象徴」とされる多くのワイナリーを設立した。彼らのようにUCデイヴィスで調査という概念に慣れた知識ある新たなワインメーカーたちが出現したことで、ワイン造り、特にシャルドネについての技術的な研究が数多く始まった。同時にヨーロッパのワイン産地を訪れたり、実際にそこで働いたりする新人ワインメーカーたちも増えた。こうしてカリフォルニアワインのスタイルはかつてないほどのスピードで多様化の様相を見せ始めたのである。
1970年代終盤、デイヴィスを卒業したレイミーの最初のワイナリーでの仕事はシミのゼルマ・ロング(Zelma Long)のアシスタント・ワインメーカーだった。1980年代になると彼はデイヴィス時代から知っていた科学者たちと共同し、シャルドネを用いた発酵温度とスキン・コンタクトの長さに関する研究を開始した。これらの研究は2つ以上の国際フォーラムで発表されており、1984年にはレイミー自身がこの研究をアメリカブドウ・ワイン学会(ASEV)のカンファレンスで発表し、その論文は広く投稿された。後年、レイミーはフォーカス・オン・シャルドネとして知られるグループのミーティングで一連のテイスティングを実施するとともに、醸造に関する調査結果を報告している。 このグループは世界中のシャルドネ生産者を4年に一度集め、技術的なテイスティングを行い、共同で実施した醸造に関する研究結果を共有するもので、この発酵温度とスキン・コンタクトに関する研究はカリフォルニアだけでなくオーストラリアのワイン造りにも大きな影響を与えることとなった。このフォーカス・オン・シャルドネとの出会いによってレイミーは世界中のワインメーカーとも交流するようになり、海外の技術について議論する機会も増えていった。
1980年代初頭、レイミーはシャルドネへの探求心が高じてブルゴーニュを訪問し、生産者たちと会ってさらに多くの醸造技術を学んだ。彼が最も産地としてのインスピレーションを得た場所として挙げたのはムルソーとピュリニーだ。もちろん彼以外のワインメーカーたちも旅をするようになり、ヨーロッパで直接学び、経験を積む機会を得るようになっていた。しかしレイミーが技術取得にかけた情熱、ASEVやフォーカス・オン・シャルドネでの研究を通じてもたらした影響、そして自身の全てをシャルドネに捧げたそのキャリアは、彼のブルゴーニュに対するひたむきな想いを際立たせるものと言えるだろう。シミの後、レイミーはマタンザス・クリークで醸造の指揮をとったが、そこで彼はシャルドネにスキン・コンタクトを使うことを完全にやめた。シャルドネに影響を与える醸造的な作業を減らすというレイミーのこの選択はノース・コーストの他のワイナリーの発展と共鳴し、1970年代に見られたフェノリックによるパワーを感じるスタイルから、1980年代のフレッシュで軽やかなスタイルの時代へ移行するきっかけとなった。
レイミーは1987年、フェノリックの影響をさらに低減するため全房圧搾をシャルドネに採用したカリフォルニア初のワインメーカーとなった。また苦みのあるフェノリックを果汁の段階で減らすため、果汁の意図的な酸化にも注力した。一方、オーク樽の使用法を変えたことも重要な変化と言える。1980年代半ばには、発酵前の果汁を濾過しない生産者も出てきていたが、レイミーはその頃に樽熟成の際に澱と接触させながら熟成を行うようになったと話している。実はディック・グラフ(Dick Graff)はすでにシャローンでその手法を用いていたのだが、当時のワインメーカーたちは現在ほど交流をしていなかったため、レイミーがこの技術を学んだのはブルゴーニュ訪問時のことだ。彼は最も大きな影響を受けた一人がルフレーヴだったと述べている。1988年、レイミーはチョーク・ヒル・ワイナリーに移り、フランスから新たな技術を持ち込んだ。発酵に自然酵母を用いる実験を始め、1991年には完全にそれに移行したのである。1980年代、発酵を自然酵母に依存しているワインメーカーはカリフォルニアにはほとんど存在しなかった。リッジのポール・ドレーパーは1969年当初から自然酵母のみを用いていたとして有名だが、当時カリフォルニアでは遠隔地間での交流はほとんどなく情報はなかなか拡散しなかったのである。さらにレイミーはレイミー・ワイナリーを設立してからはMLFも完全に自然にゆだねるようになった。当時はMLFを確実に起こすことが難しかったため、生産者たちはMLFを起こすために市販の乳酸菌を用いることが多かった。
1996年、レイミーはカーネロスにあるハイド・ヴィンヤードで作ったシャルドネだけを用いる、自身の名を冠したワイナリーを設立した。その後数年間で彼は別の畑名を記したシャルドネ、シャルドネ以外の品種のワイン、さらにノース・コーストで著名な畑の名を記したシャルドネなどを次々と生み出した。2000年代初頭、レイミーは自身のワイナリーに専念する前の最後の仕事としてナパ・ヴァレーのラッドでワイン造りを担当した。シミでの初仕事以来、一貫してレイミーのキャリアの中心にあったのはシャルドネだ。樽発酵を行い、澱とともに熟成させ、自然の酵母及び乳酸菌を用いる。さらに、レイミーのシャルドネはシングル・ヴィンヤードであれば20か月、産地名ワインでも12か月の熟成を行う。レイミーがシャルドネのスタイルとして目指すのはリッチさとフレッシュさのバランスをとることであり、エレガントに熟成するクラシックなスタイルの美味しいワインを造ることだ。
こうしてカリフォルニアワインが打ち出したフレッシュさと複雑さは1980年代に世界から注目を集めた。ヨーロッパの生産者たちがコラボレーションを申し出たりノース・コーストの畑を購入したりするようになったことで、そのスタイルに更なる小さな進化のさざ波が立った。コラボレーションの最も早い成功例であるオーパス・ワンはグローバルな視点を持ったロバート・モンダヴィが仕掛け、1979年に発表されたものだが、ナパ・ヴァレーのカベルネ主体のブレンドワインのみに注目したものだった。同様なジョイント・ベンチャーでシャルドネに注目したものは、ロデレールのアンダーソン・ヴァレーのワイナリーやテタンジェのドメーヌ・カーネロスなど、スパークリングワインから始まった。この時期、モンダヴィもまた、海外資本、例えばイタリアのアンティノリ家にもインスピレーションを与えている。彼らは後にアンティカ・ワインのシャルドネとカベルネに使われることとなる畑をアトラス・ピークの斜面に開拓し始めた。
ノース・コーストでレイミーのようなワインメーカーたちがブルゴーニュから醸造技術を盛んに仕入れていたころ、セントラル・コーストのワイン造りもようやく、その独自の個性を発揮し始めた。1980年代初頭にはサンタ・バーバラ・カウンティでブドウの栽培面積が拡大し、独自のワイナリー・ブランドが立ち上がった。注目すべきはオー・ボン・クリマのジム・クレンデネン(Jim Clendenen)がブルゴーニュでのワイン造りの経験をサンタ・マリア・カウンティの畑に持ち込んだことだ。彼のアプローチは全体的にフレッシュさとリッチさのバランスを取るスタイルに注力したもので、ブルゴーニュのクラシックな醸造技術を利用しながらカリフォルニアのブドウを使ってワインを造る、レイミーのそれと似ている。オー・ボン・クリマのシャルドネもまた、その個性を発揮するまでに5年は瓶内で熟成させる必要があることで知られており、その後10年目ぐらいまで、太平洋の冷却効果を享受した、甘さのないフレッシュさと緊張感を見せつけるワインだ。
クレンデネンの影響はそのスタイルだけではなく、世界での認知度、そして次世代のワインメーカーにまで及ぶ。クレンデネンはセントラル・コーストの他のどのワインメーカーよりも文字通り「世界中」をめぐり、オー・ボン・クリマのマーケティングに励んだ。そのおかげでカリフォルニアの中でも目立たなかったこの地域が国際的に認知されるようになったのである。オー・ボン・クリマのワインはヨーロッパやアメリカだけでなく、アジアの僻地でも簡単に見つけることができる。こうすることで、ノース・コーストのモンダヴィ同様、クレンデネンはセントラル・コーストで若手の生産者たちが世界の市場へ到達できるよう道を切り拓いたのだ。また、クレンデネンは継続的に若手を指導し、インターンシップを通じて醸造所で彼らを鍛え、自身のワイナリーの一部を彼らのための醸造スペースとして提供した。だからこそ、フレッシュさとフレーバーの両方に注目しながら発酵と熟成を樽で行うというクレンデネンのこだわりが、この地域の若いワイナリーが作るシャルドネに現在でも反映されているのだろう。
進化するナパのシャルドネ
ノース・コーストに話を戻すと、こちらでも次の変化が起こり始めていた。シャルドネの造りはレイミーのそれとは明らかに対照的だったが、同じ時期にデイヴィスを卒業したジョン・コングスガード(John Kongsgaard)もまた、シャルドネに対するアプローチでその影響力を増していた。デイヴィス入学前の1975年、ストーニー・ヒルでの仕事がコングスガードの最初の仕事だった。当時彼はフレッド・マクレア、マイク・ケリーニ、そしてナパ・ヴァレーのシャルドネにとって重要なもう一人の人物、リック・フォーマン(Ric Forman)とともにワインを造っていた。 コングスガードがワインを造りたいと思うきっかけとなり、シャルドネの基本を叩き込まれたのがストーニー・ヒルだったのである。コングスガードによると、この経験で彼が得た最も重要な学びの一つはシャルドネの樽発酵が、可能というだけでなく、安全で有益であるという点だったそうだ。ナパ・ヴァレーでは大半がステンレス・タンクに依存した時代だったにも関わらず、ストーニー・ヒルは木製の容器を使った手法にこだわり続けていたのだ。
その後すぐ、コングスガードはクームスヴィルのはるか西、両親の所有していた土地を自身の最初の畑とし、ブドウを植え始めた。現在「ザ・ジャッジ(ナパ・ヴァレーの判事だった父に敬意を表してつけた名)」と呼ばれるこの場所に彼がシャルドネを植えることにしたのは近所に住んでいたアンドレ・チェリチェフ(André Tchelistcheff)の勧めによるものだった。チェリチェフは1973年にボーリュー・ヴィンヤードを引退していた。ボーリューは高級なカベルネ・ソーヴィニヨンで知られていたが、チェリチェフは上質なシャルドネを造ることにも強いこだわりを持ち続けていた。彼はナパ・ヴァレーの比較的冷涼な場所にありユニークなまでに岩がちな「ジャッジ」がシャルドネにとって面白い場所となるはずだと確信していたのだ。一方ストーニー・ヒルで働いた後、コングスガードはカベルネ・ソーヴィニヨンについても学ぶため、スタッグス・リープ・ワイン・セラーズのワーレン・ヴィニャルスキ(Warren Winiarski)と共に働いている。
デイヴィスを卒業後、コングスガードは最初のワイン造りの仕事をソノマで始めた。そのバルヴェレーネ(Balverene)はその後すぐになくなってしまったが、彼はそこで赤ワインの造り手、ダグ・ナール(Doug Nalle)と肩を並べて白ワイン造りに携わった。プロジェクトは短命に終わったものの、ナールとコングスグガードはかなり自由にワインを造ることができたという。バルヴェレーネ解散後、1983年にコングスガードはニュートンに雇われ、1996年まで働いた。所有者のピーター・ニュートン(Peter Newton)はフランスのワインに深く傾倒している人物だった。コングスガードのワインメーカーとしての知識を深めるため、ニュートンは二つのことを取り計らった。まずコングスガードにワイン用の予算を充て、ブルゴーニュとボルドーを定期的に飲む機会を与えコングスガードがそれらについて感じたことを彼と共有させた。またコングスガードを年に1度フランスに行かせ、両産地のワインメーカーに会えるよう取り計らった。コングスガードが長期の樽熟成に注力している生産者を探し始めたのはニュートンで働き始めてすぐ、この頃のことだった。
1988年、コングスガードはリスクを承知でその手法をカリフォルニアに持ち帰った。彼はカリフォルニアで初めて天然酵母を用い、自然なMLFを行い、樽発酵ののちに樽熟成を2年行い、濾過をせずにシャルドネを造った。そうして造られたワインが安全なだけでなくおいしいものであると仕入れ担当者を納得させるため、彼は当初営業活動に行く際には2つのロットを造り携えることにしていた。一つのロットはカリフォルニアで通常行われているように濾過をしたもので、もう一つは無濾過のものだ。ワインをブラインドでテイスティングさせると、仕入れ担当者は常に無濾過のほうを好んだ。コングスグガードの説明は論理的で、MLFを完了させているため微生物学的安定性を目的とした濾過は不要になるし、長期の樽熟成により固形物が沈殿するためワインは非常に安定し、抜栓後数日経っても表現力が増すことすらあるというものだった。
1996年、コングスガードは自身の名を冠したワイナリーを設立するためニュートンを離れ、以来現在まで同じスタイルでシャルドネを造り続けている。2016年までは100%フレンチ・オークの新樽で発酵させていたが、2016年にその比率を80%程度まで下げた。これほどの新樽比率の高さにもかかわらず、ワインは2年目まで同じ樽の中に置くため、1年間新樽で熟成させたものよりもその影響は弱く感じられる。ワインが落ち着くに従い樽の影響が弱まるためだ。新樽比率を変えたのと同時にコングスガードは収穫をやや早め、比較的フルボディで芳醇なスタイルになりがちだったワインにフレッシュさを与えることにした。
ここで注目すべきは、コングスガードがワイン造りを典型的な地表のワイナリー設備から標高の高いアトラス・ピークに掘削したカーヴの中で行うよう変更した点だ。山の懐に掘られた洞窟は自然のままで温度が低く保たれる。そのため発酵には明らかに時間がかかるようになり、時には完了するまでに1年を要することもあった。コングスガードによれば長期の熟成は、発酵が長引くことに伴う不安をすべて取り除くものだそうだ。上述のような環境下でもMLFはアルコール発酵よりも先に完了することが多く、ワインのフレーバーに独特な個性を与えてくれる。コングスガードはそれをこの洞窟の持つテロワールの一部だと考えている。また長期熟成に伴ってセラー内でゆっくりとした蒸発が起こるため、最終的なアルコール度数がほんの少し上昇する。もともと比較的熟した状態でブドウを収穫しているためワインは最終的にかなり骨太になり、ザ・ジャッジのシャルドネの最終アルコール度数はヴィンテージによって14.5%から16%ほどだ。カリフォルニアのシャルドネのアルコール度数がここまで高くなることは十分あり得るとはいえ、それを正直に公開している点でコングスグガードは別格だ。長期熟成の影響はワインに独自の緊張感を与え、ただリッチでフルボディなワインであるだけでなく、幅広い複雑さをもたらしてくれる。ただし、このスタイルはテイスターによって評価が分かれることも確かで、10月のMWセミナーでMWたちの好みは両極端だった。
コングスガードのここ数年のスタイルには、息子のアレックス・コングスガード(Alex Kongsgaard)が参加した時期からさらにフレッシュさが加わっている。アレックスは父とは違いデイヴィスで学んではいないが、ワイン造りを現場の実践で学んだ。また、地元で定評のあるワインメーカーとテイスティングや勉強の機会を共にし、例えば、圧搾技術の向上のためレイミーと時間を過ごすよう取り計らったこともある。
歴史的視点から見ると、コングスガードは2段階の重要なスタイルの進化を体現していると言える。第1段階である1970年代は一般的に醸造所内での技術に重きが置かれており、新たな機材が利用可能になるにつれ生じた問題点を技術的な調整で補う傾向にあった。例えば、ステンレス・タンクはスキン・コンタクトにつながり、スキン・コンタクトは濾過の多用につながったように。そして第2段階でレイミーのような生産者たちはワインに透明性を持たせるため、どの技術を使わないか、あるいは最小限にすべきかを見出すことで技術への偏重からエレガントさを取り戻すことに成功した。一方コングスガードのような生産者たちは別のアプローチをとり、技術的なワイン造りという枠組みを超え、直観を重視した。結果としてはレイミー達同様、醸造所内での不必要な技術を最小限にするというさらに強い意識を持つようになったのである。
1980年代終盤にはいわゆる「ビッグなワイン」の人気が再燃し、1990年代半ばにはスタイルとして真に確立されたものとなったが、以前のそれとは少し違っていた。1970年代のワインの重さはスキン・コンタクトに由来するものだったが、1990年代のそれは遅摘みに由来するもので、生産者によってはそのようなワインのバランスをとるための酒石酸添加や、培養酵母を用いた発酵を避けることすらあった。当時のワインは熟度もアルコールも高く、多くの場合はpHも高く酸が低かった。さらにブドウの熟度が高いことで残糖のあるワインも少なくなかった。その結果生まれたフルボディで余韻に甘みを感じるワインはまさにパワーのワインだったが、1970年代のフェノリックの存在による重さとはアルコールと熟した果実味に重点を置いている点で一線を画していたのである。このような1990年代から2000年代半ばにかけてのパワフルなワインはカリフォルニアのシャルドネの典型として位置づけられることが多く、いわゆるグロッサリー・ストアなどで販売される日常的なシャルドネのスタイルとして定着した。カリフォルニアのシャルドネの畑のブドウの多くはそのレベルのワインに使われるようになっていった。ただ申し添えておきたいのは、最近はグロッサリー・ストアのシャルドネですら、幅広いスタイルが入手可能であるという点だ。
大衆の興味がリッチなスタイルのワインへ向かうようになった一方、クラシックなアプローチにとどまる生産者も存在した。また、アルコールが高くリッチな表現は必ずしも残糖に依存したものではなく、単に熟度が高いだけという場合もあった。いずれにしても、熟度の高いスタイルはロバート・パーカーやワイン・スペクテーターなど評論家たちの注目を集めることとなり、その流れは2000年代へと続く新しい象徴的なワイナリーやワインメーカーの進出ラッシュを生み出した。だが、この熟度の高いスタイルの急激な増加は消費者の間に、ある種の不和を生み出すこととなる。
パーカーやワイン・スペクテーターには熟度の高いスタイルを造るお気に入りの生産者がいて、ノース・コーストではマーカッサン、キスラー、デュモルなど、サンタ・バーバラ・カウンティではブリュワー・クリフトンなどが知られている。これら熟度の高いスタイルは重さとともにニュアンスを持ち合わせていると認識する人たちも一定数存在したし、キスラーやブリュワー・クリフトンのシャルドネは重さだけではなく熟成のポテンシャルもあることを証明していた。一方、ワイン愛好家の中には、熟度の高いワインは単に重さだけであり、それを超える魅力が伝わらないと感じる者も出てきた。そうしてテイスターたちは熟度の高いワインだけでなく、カリフォルニアのシャルドネ自体に背を向けるようになったのである。中価格帯からグロッサリー・ストア・レベルのワインに残糖が多くみられるようになったことも、熟度の高いワインが避けられる傾向に拍車がかかった大きな要因だ。シャルドネはそのようなスタイルとひとくくりに結び付けられ、ワイン愛好家たちの間で「シャルドネ以外なら何でも(Anything But Chardonnay)」、いわゆるABC運動が生まれるようになった。だが、その裏では人知れず次の改革も進んでいた。
1990年代から2000年代中盤にかけてアルコールの高いワインが定着した時代ですら、マウント・エデン、ハンゼル、ストーニー・ヒル、オー・ボン・クリマ、レイミーなどクラシックな生産者たちが従来からの控えめなスタイルを保ち続けていた点は注目に値する。一方大手に買収されたBVやシャローン、モンダヴィなどのワイナリーは、新たなオーナーが新しい流行を追いかけ、クラシックなのはその名前だけというケースもあった。かつての方針を守ってきた人々がクラシックなスタイルを維持するということは、熟度の高いスタイルが世の中を席巻していた中で(当時は極わずかではあったものの)スタイルの多様性に余地を残すこととなった。2000年代には、ノース・コーストでも次の世界的な流行が感じられるようになり、カリフォルニアの果実味にヨーロッパの繊細さを取り入れようという動きが出てきた。有名どころではカーネロスに畑を所有するハイド家(初めての植樹は1970年代)とブルゴーニュのオベール・ド・ヴィレーヌ(Aubert de Villaine)が共同し、新世紀の初めにHdVワイナリーを立ち上げたことだろう。そこではフランス人ワインメーカー、ステファン・ヴィヴィアー(Stéphane Vivier)がヴィレーヌの指導力とハイドの畑での洞察力を昇華させ、フランスの視点でカリフォルニアのフレーバーを尊重したワインを造り出すことに成功した。
( パート4に続く )
参考文献
・Gerald Asher, 1990, ‘Chardonnay: Buds, Twigs and Clones’, Gourmet
・Robert Benson, 1977, Great Winemakers of California
・Doris Muscatine, Maynard Amerine, Bob Thompson, 1984, The Book of California Wine
・Thomas Pinney, 1989, A History of Wine in America, Volumes 1 & 2
・Frank Prial, 2001, Decantations: Reflections on Wine
・Nancy Sweet, FPS, UC Davis, 2007, ‘Chardonnay History and Selections at FPS’, FPS Grape Program Newsletter
・George Taber, 2005, Judgment of Paris: California vs France and the historic 1976 Paris tasting that revolutionized wine
・FPS Grapes, Grape Variety: Chardonnay
・Focus on Chardonnay (proceedings of a four-yearly meeting of Chardonnay producers from around the world, available from the participating wineries only)
・University of California Oral History Project: including Ernest Wente, Wente Family, Mike Grgich, Zelma Long, Eleanor McCrea, Maynard Joslyn